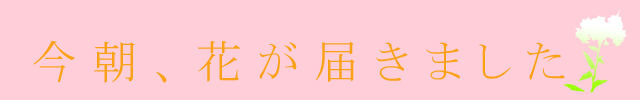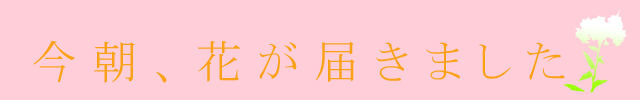
| 「俺はあなたに春の訪れを知らせる事が出来ればそれでいいのです。」 そう言って優しく笑った黒尽くめの案内人を思い出すのは凍てつくような寒さが少し和らいだからだろう。もうすぐ春だ。砂隠れでは花が咲き乱れる事はないが、それでも他の季節よりは花が咲く。その花々を眺めながら我愛羅はため息をついた。あの案内人がこの地を去って随分と経つ。暖かい春がやってきて氷が溶け、木の葉と知り合いになった。自分にも目標が出来て今は風影の役職にもついている。小さかった我愛羅はもう立派な青年になっていた。 緩やかな風が花を揺らし、色素の薄い髪を揺らす。膝に頬杖をついてしゃがみこんでいた我愛羅の額に背丈の高い花の花弁があたってくすぐったい。まどろむように目を閉じると表通りの賑わいが風に乗って聞こえてきた。今日は東の国の商人が来ていた筈だ。珍しい花々を入手したらしい。その為表通りは大賑わいで、我愛羅のいる縄で括られた花壇には誰もいない。だからこんなにだらけた姿をしていられるのだが。 「はじめまして」 穏やかな声にはっと振り向くと黒尽くめの人が立っていた。一瞬あの案内人かと思ったが髪の色や目の色が違う。よく見れば顔の造作も中世的ではあるがすっきりとした目鼻立ちだった彼女とは違い、何処となく甘さを含んだ顔立ちで、黒い服も着物ではなく軍服だ。背が我愛羅よりも高く、細い体は軍人と言うよりは舞台が似合うだろう。しかし一見優男に見えるこの人が気配もなく自分に近づき、気の流れを乱さないのは、やはり只者ではない。 その人は目が合うとニコリと笑って 自分の名は相葉だ、と相変わらずの柔らかい声で口にする。女性であることに多少驚きながらも自分も名乗ると「知っているよ」と笑われた。その拍子に彼女の腕に抱えられた白い小さな花が小刻みに揺れる。黄緑の細い茎の先に水滴をたらしたように点々と咲く、本当に小さな花。小指の爪よりも小さい為我愛羅は最初それが花であったのかすらわからなかった。ただ一つ一つの花弁は小さいものの抱え切れないほどの花のせいで彼女の印象的な黒い服も柔らかな笑顔も霞ませる。 「本当は本人が直接渡すのがいいのだろうけれど、如何せん今の時期は忙しくてね。ほら、あの子は案内人だし、生命が息吹く今は導かなければいけないモノが多いのさ。だからどこもかしこも彼女の話で持ちきりなんだ。」 当たり前の世間話をするように彼女はそう捲くし立てながら抱えきれない花を我愛羅に渡す。あまりにも自然な動きに気がつけば腕に少しばかりの重みを感じ、自分の濃い色の服が霞んで見える。目を丸くして相手を見ると、は悪戯が成功したときのような笑みで片目を閉じて口元を吊り上げていた。白い小さな花たち。そては本に乗っていたある写真を思い出させる。あの日案内人が話してくれた故郷の情景を思わす白い氷の結晶たち。そう、まるで・・・ 「雪のようだろう?」 笑いを含んだ声は心を躍らせるような響きがある。知らず知らずのうちに自分の口元にも笑みが浮かぶのを我愛羅は感じた。やわらかい風に沢山のカスミソウが揺れる。見た事のない情景に心を躍らせたあの日、雪が見たいと言った自分に彼女が微笑んだのを思い出す。 約束は長い時を経て、果たされた。 |