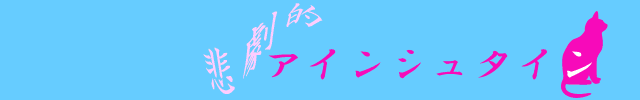|
はIQ200をもつ天才児だ。 十歳でアメリカの名門大学を出たらしい。今彼女は中学生をしている。テストの点数はよくもなく悪くもない。普通の十四歳の女の子。しかし俺はが嫌いだった。 頭がいいのに普通の点を取る彼女が大嫌いだった。 「。」 呼ぶとうっぷしていた彼女の頭が微かに動く。放課後の教室。夕日が窓を染める。俺と彼女以外誰もいない。意識はあるのに未だに動かない彼女に溜め息を付き、俺は手に持っていた黒板消しを黒板に置いてが座る前の席に座った。書き忘れていた学級日誌を書く。窓から入る風が気持ちいい。もう一人の日直は俺に仕事を押し付けて帰ってしまった。汚い字が日誌を埋めていく。後ろで呻くような唸るような声が聞こえた。 は時々下校時間まで机にうっぷしている事がある。(何故俺がそんな事知っているかと言うと獄寺君が休みの時限定で日直を押し付けられているからだ)そして彼女が天才児だと知ったのはついこの間だ。リボーンが これお前のクラスメイトだろと古びた新聞を持って来たのは記憶に新しい。隅に今より幼いが映っていた。“十歳の天才少女”リボーンが読み上げた。 「なんで普通の点取るの?」 今日の時間割を思い出しながら訊ねると彼女の呼吸がぶれる。先生達はに対して何処かよそよそしい。彼女が何か意見しようとすると身構え、そのくせテストを渡す時は冷え冷えする様な表情。(さんはもっと出来るはずよ。どうしてこんな点数取るの?)そう言われるたびに彼女は曖昧な笑みを洩らしていた。 「新聞見たよ。アメリカの。隅にの写真が載ってた。」 頭良いんでしょ 大学までスキップしたって聞いた なんで中学生してるの 就職とかすればいいじゃん こんな事して楽しいの には簡単な勉強だろ 本当は見下してるんじゃないの 日誌の空欄が埋まっていく。オレンジが広がる。は何も言わない。苛立つ。その沈黙がダメツナである俺を見下している気がした。普通の点すら取れない俺を。 「見下してなんか、ない」 掠れた声が後ろからした。簡単な勉強じゃない、頭が良くたって損ばっか、 「余計な口出しはするな、質問するな、見下すな。なのに平均的な点を取るとバカにしてるのか、本気を出せ。先生達はそんな事ばっかり。親は私が問題で離婚した。」 ぽきりと芯が折れた。後に続く文字を考えられない。俺はが嫌いだった。先生達は俺を見ていつも彼女を見習えと言う。お前とを足して二で割ったら丁度いいんだろうなと。何をやってもダメな俺。出来すぎる彼女。なのには凡人に振舞う。腹が立った。どうせなら見せ付ければいいのに。それなら俺もこんな事思わないのに。わざと問題を間違えてわざと平均的な点数を取る。馬鹿にしている。が呻く。 「大学なんて行きたくなかった。小学校に行きたかった。友達が欲しかった。ク−ロンの法則より鬼ごっこがしたかった。フランス語の勉強よりアニメが見たかった。家族揃ってご飯食べて、友達と遊んで、恋して、笑って、時々泣いて。私は、私は私は」 「普通の女の子になりたかった。」
|